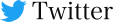元旦に開く喫茶店
January 3rd, 2021
大晦日から元旦にかけて京都にいた。今年はやはり街に人がとても少なかった。
当たり前だが元旦にやっている店は少なく、開いているのは中心部の繁華街のチェーン店や観光客向けの店などが中心である。スタバなんかでも一部の店は休み、一部の店が少し遅い時間から開いていた。
小さな個人店たちは普通に三ヶ日は閉まっているわけだが、実は平常通りにやっている或る業態があった。それは街の外れの何てことない喫茶店たちである。
レトロな雰囲気を売りにしているでもなく、名店と言われることもなく、その街の人たちもなんとなくしか知らない。ただただ街の中で40年50年経った感じの店。爺さんか婆さんが一人でやっている。入りづらいし、特別に美味いわけでもない。お客も基本的に常連のお爺さんとお婆さんである。
そんな喫茶店が、元旦の朝に数件、開いていた。僕は東京の下町でも他の街でも、そういう喫茶店に足を踏み入れることがある。理由は自分でもよくわからない。レトロな名店に入るのとは多分違う。少なくとも珈琲の味や内装や、名店訪問リストを制覇していくことなどは目的にはなりえない。
僕は元旦の朝10時すぎに、ホテルで朝食を一応食べた後の散歩の途中で、寺町通のそんな喫茶店の様子がどうしても気になって足を踏み入れることにした。
そもそも彼らなぜ元旦の朝に開けているのか? オーナーの爺さんは暇なのだろうか?家族が集まっておせちを食べることももうしばらくなくなっているのかもしれない。だか本当の理由は違う。彼はある種の使命感として、”やらねばならない”のである。
その小さな古びた空間には店主のお爺さんの他に3人がいた。お婆さん1人と、お爺さん2人。お婆さんは、我が3歳の娘に微笑んで「おいくつ?可愛いわねぇ」と声をかけたあと、運ばれてきたカレーライスをゆっくり食べ始めた。
お婆ちゃんはこの京都でおそらく一人で暮らしているのだろう。彼女はこの日の朝、おせちを食べるより、”いつもの日常を過ごすために”そこへ来たのである。二人の爺さんも、或いは店主の爺さんも、同じである。いわば彼らにとってのモーニング・ルーティンである。店主はそうした街の日常のために、年の始まる日も変わらず、珈琲やカレーを出す。
ここは商業空間ではなく街の”コモンズ”、つまり日常生活の中にある共有地である。
とはいえここは不特定多数のための、”みんな”のための場とはいえず、或る一部の人々の日常の生活空間である。しかし街には一応開かれており、社会(public)に接続している。
これに近い性質が街場のスナックにもあるけれど、喫茶店は”黙っていられる場所”である。ここで正月に常連のためにおせちの会などを企画してしまっては、そこに訪れる人たちや店主のそれまでのある種の距離感は失われるかもしれない。会の告知がここに置かれることはあっても、行われるのは他の場所であるべきなのだ。
語らずともその空間に身を置き存在を承認し合う関係、あるいは心地よい自由がそこにはある。そこに流れるある種の安心感とか、彼らのある種の居心地とか、そうしたものを感じるのが僕は多分、好きなのだ。
その店の店主はかつては夫婦で店を営んでいたかもしれない。店を始めた頃はきっと、今どきのコーヒースタンドのようにハイカラだったのだろう。いま新たに開かれる個人店のカフェたちも、形は違えどやがて同様な境地に至るのかもしれない。
古い店たちが少しずつ新しい素敵な店に変わっていくその狭間に残された街場の謎の喫茶店たちは、世代を超えて生活が息づくこの偉大な都市の端々で、こうして新たな年を積み重ねていく。
街の中の多様な空間が維持されていくことと、現代の”最適化”は全く異なる意味を持つ。ジェントリフィケーションとは、街の「価値」が上がってしまうことで元々の住民が住めなくなるという意味だけではなく、彼らの暮らしの基盤であるささやかなコモンズが失われていくことも意味するのだ。
*もしかすると、こう言う人がいるかもしれない。「あのなぁ、お前。年始は年始で一定のニーズがあるから開けてンだよ。売れるンだよ。別に社会的使命感とかじゃねーよ。てかコモンズとかうぜーし」と。
そう思った人は要注意だ。ある場所を営み続ける人の思いやプライドへの想像力が欠け始めている・・(知らんけど)